こんにちは!ikkiです。
書籍紹介のコーナーでは、平凡な私が様々な挑戦をしていく上で役に立った書籍を紹介します。
今回は、コーチングに関する書籍です。
コーチングとは
コーチが対象者との対話を通じて、対象者が目標を達成できるよう支援するコミュニケーション手法。対象者の能力や可能性を最大限に引き出すことを目的としており、知識やノウハウを相手に教えるティーティングとは対照的に、問いかけを通じて対象者自身から様々な考え方や行動の選択肢を引き出す技術。
コーチングの素晴らしさを学べると共に、読んだ後、「行動しなければ!」と思わせてくれる一冊ですので、是非一度読んでみてください。
書籍の概要
Amazon.co.jpより
ザ・コーチは物語調になっており、ストーリーを楽しみながら、夢の描き方やその実現方法について学ぶことができる自己啓発本です。
ストーリーのネタバレにもなりますので、ストーリーをじっくり楽しみたい方は、まずは書籍を手に取っていただくことをおすすめします。
主人公の星野(36歳)は住宅メーカー営業部の万年係長。人柄もよくそれなりに人望もあるのだが、肝心の販売成績がなかなかふるわない。ある日、期待を寄せていたお客に逃げられた星野は、むしゃくしゃした気持ちを静めるために、いつもの公園に出かけた。そこに偶然現れたのは、どこか見覚えのある一人の老紳士だった……。
ザ・コーチ 最高の自分に出会える『目標の達人ノート』 -谷口孝彦- (プレジデント社)
主人公の感じからすでに感情移入できてしまう方も多いのではないでしょうか笑
この老紳士と出会いが主人公の人生を大きく変えることになります。
ちなみにこの老紳士はある大企業の会長で、主人公はこの人物から週1回公園での特別授業を受けるようになります。
その特別授業の中で、主人公は夢の描き方やその実現方法といった成功の秘訣を学ぶことになるのです。
心に刺さった内容
ここからは、ザ・ゴールを読んで私の心に刺さった内容を紹介していきます。
ここでは夢、目的、ゴール、目標という言葉が出てきますが、この書籍ではこれらを明確に区別することの大切さも語られています。
- 夢:将来実現したいと、心の中に思い描いている願い
- ゴール:目的のための最終的な目印(目的は成し遂げたいと目指す事柄)
- 目標:ゴールまでの途中の目安や通過点
そしてこれらを図に表すとこのような形になります。

夢という目的の実現のために明確なゴールを設定し、このゴールに到達するために具体的で確実な行動の一つとして目標を定める。
是非この図を意識しながら以降読み進めていだだければと思います。
盲点と焦点とチャンス
子供が生まれるとなったとき、やたら小さい子が目にとまるようになるという経験はないでしょうか。
別にその地域に住む子供が突然増えたわけでもないのに、これまで気にならなかった子供の遊び声、登下校の様子などが突然目に留まるようになる。
これは子供に対する関心が高まったことによる現象です。
世の中にある情報の多くは、誰に対しても平等に公開されていますが、その人が何に関心を持っているかによって、目に留まる情報は異なってきます。
よく成功している人は夢や目標をしっかりと持っているといいますが、いつも夢や目標を明確に持つことで、それらに関する情報をキャッチできる確率が高くなり、漠然と生きている人と比べると入ってくる情報の質と量が全く違ってくるのです。
情報はチャンスであり、そのチャンスを掴めるかどうかは、そこに意識が向いていて、脳がキャッチできるかどうかにかかっています。
そして明確な夢、目標を持つことで、それに対する知識もどんどん増えていきます。
車が欲しいと思って、車の性能などについて調べていると、車に全く興味がない人に比べると持っている知識に大きな差が出てきますよね。
つまり、これから何かに挑戦しようとする人は、夢や目標を明確にし、それを持ち続けることが大切になります。
まずは自分の夢は何か考えてみることから始めてみましょう。
小さく始める
「夢や目標を立てることが大切です。」
そんな当たり前のことはわかっているよ!と思いつつも、実際には夢や目標、ゴールを持たない人が多いのはなぜでしょうか。
一つの原因として、そこに妨げになるもの、つまりはブレーキが存在すると考えられます。
ブレーキとなるものには様々なものがあります。
夢を語ることで批判された経験、達成できなかった時の人格否定、夢や目標やゴールに対する無知、変化に対する恐れ、、、
いくつか思い当たる節があるという方もいるんじゃないでしょうか。
では、このように多くのブレーキが存在する中で、夢やゴールをしっかりと掲げるにはどうしたら良いでしょうか。
その一つの解決策として挙げられるのが、「小さく始める」です。
ゴールや目標を立てるのが難しいと感じた時、その大きさを変えると立てやすくなることがあります。
登山初心者の人が「エベレストに登頂する」というゴールをいきなり立てても、途中で挫折してしまう可能性が高いですが、「まずは地元の登りやすい〇〇山に登頂する」、「次は富士山に登頂する」と小さなゴールを段階的に立てていくのです。
これによってゴールや目標を立てる訓練にもなり、大きな夢を立てるためのブレーキを減らし、その実現可能性さえも高めてくれるのです。
俗にいうスモールスタートと同じですね。
私自身、大上段に構えて大きなゴールを立ててしまい、知らず知らずのうちに挫折してしまっているという経験を何度もしてきました。
小さな目標をコツコツ立てては成し遂げていく。
この書籍を読んで、成功体験を積みながらそうやって少しずつ前に進んでいくことの大切さを感じることができました。
目標を与えるということ
私が職員マネジメントを行なっていた時、目標管理にとてつもなく難しさを感じていました。
いわゆるMBO(目標管理制度)と呼ばれる、職員自身が具体的な目標を立てて、それを実行、評価していくという評価制度でしたが、これを運用する上での職員のモチベーション管理がなかなかうまくいきませんでした。
「立てる目標がない。」
「目標を立てたけど、会社にやらされてる感がある」
いろんな理由でモチベーションが保てず、よかれと思って導入されている目標管理が、ただの負担になってしまっていました。
ではなぜ、多くの先進的な企業で導入されて実績もあるはずの目標管理制度が、うまく機能しないのでしょうか。
この原因を解き明かすのに、「やらされてる感」というのが一つの鍵になります。
会社のゴールは明確です。
事業拡大する、職員を養う、顧客に安定したサービスを提供する、、、想い(目的)はそれぞれですが、明確なゴールは「利益を上げること」ただ一つです。
問題はこれをただただ押しつけて、それにつながる個人目標を立てただけでは、職員は自分で立てた目標のはずなのに自発性を失い、「やらされてる感」を強く感じてしまいます。
これを防ぐには、目標管理する立場の上司が、部下の価値観や未来の夢をしっかりと聞き、部下の個人的な目的と会社のゴールの接点を一緒に見つけるのがポイントになります。
(例)
会社:営業成績をアップさせたい
個人:営業にあまり興味がない。いつか起業して、独立する夢がある。
→起業して稼ぐためには自分で顧客を獲得する必要がある。そのための能力を高めるために営業力アップを志してはどうか?
戦後の日本では、国民全員が「もう一度日本を復活させて、豊かな生活を取り戻す」というある種共通の目的を持っていたため、会社のために頑張るということに大きな反発はあまりなかったと言います。
ですが、現代は物で満たされ、心が求める目的を満たすために働く人がほとんどです。
そんな中で、昔のように「会社のために、、、」と言われても、いわゆる現代の若者にはなかなか響くことはありません。
このことを理解し、部下の目標設定を適切にサポートしてあげるのが、優秀な上司なのではないでしょうか。
今現在、部下のマネジメントで悩まれている方には、是非読んでいただきたいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここで取り上げた内容の他にも、たくさんの学びがある書籍です。
ちなみにこの物語の主人公は最終的にプロコーチとして活躍し、書籍を出版するなど大きな成功を収めています。
人に導かれ成長していった人が、人を導き成長させるようになる。
こんな素敵なサイクルを回せる人間に自分もなりたいものです。
みなさんも是非この書籍を読んで、夢やゴール、目標を立てるのに役立てていただければと思います。
ではまた!
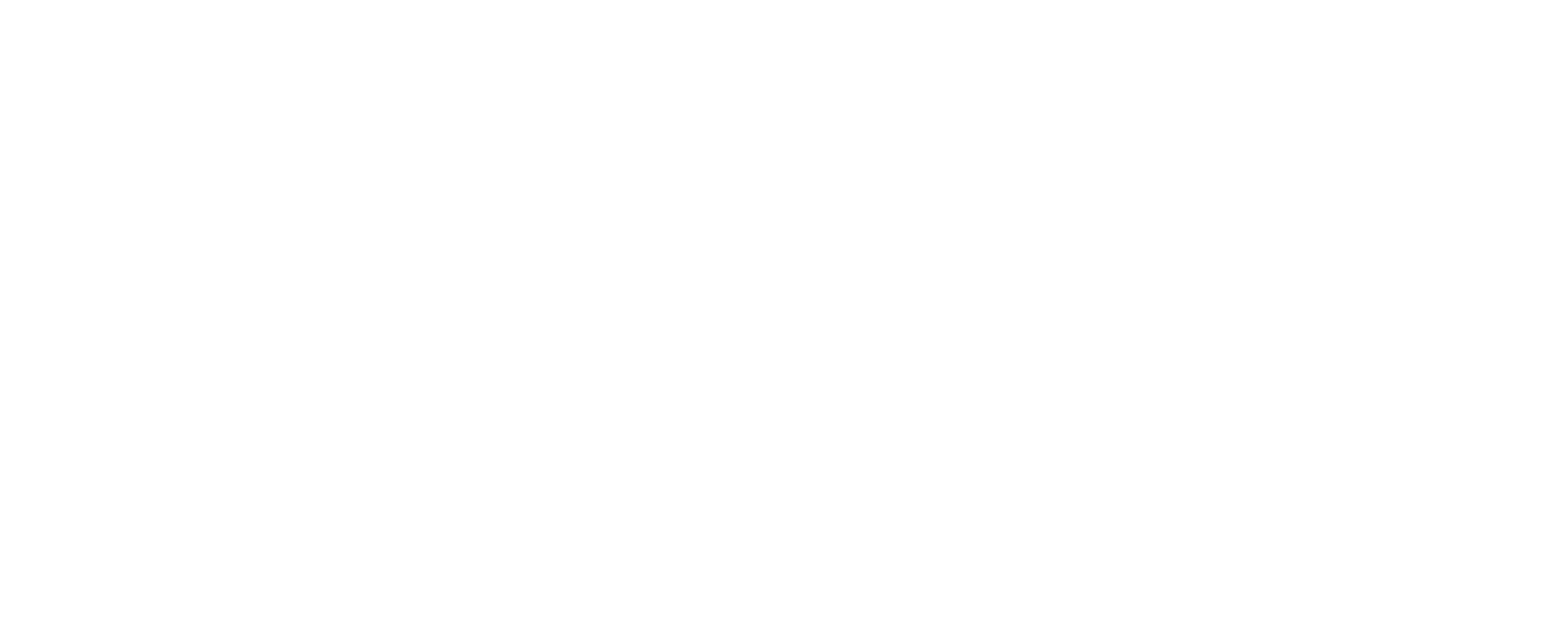





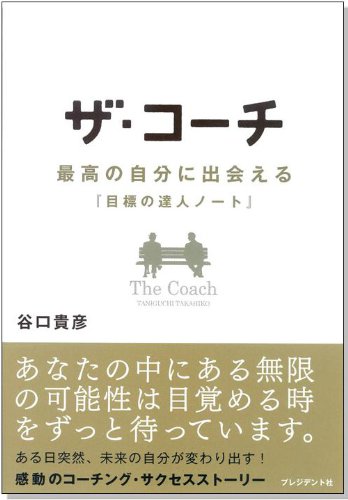

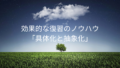
コメント